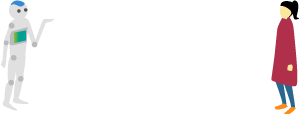小森 理
Society 5.0研究所は「三菱創業150周年記念事業委員会」から御支援を頂き、2020年に創設されました。コロナ禍の影響で実質的な活動は2021年からとなりましたが、その年の9月には成蹊大学Society 5.0研究所開設記念フォーラムを開催することができ、本格的な活動を開始致しました。 本研究所では主に①学融合的な研究プロジェクトの推進、②社会・地域課題解決のための連携プロジェクトの推進、③これからの社会を担う若い世代の人材育成、を3つの柱として取り組んでおります。
不確実性や不透明性に満ちた時代を表す言葉にVUCAがあります。2001年の同時多発テロ勃発のあたりから軍事用語として用いられた言葉で、それぞれ、Volatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)の4つの名詞を表現しています。また生成AIの台頭に伴い、人間の心理的内面性を表現している4つの形容詞からなるBANIの用語も最近注目されるようになりました。このような混沌とした時代にあって、我々が目指すべき社会としてSociety 5.0が日本政府によって提唱されました。狩猟、農業、工業、情報の社会を経て、サイバー空間とフィジカル空間を高度に融合させたシステムにより、「経済発展」と「社会的課題の解決」を両立する人間中心の社会です。また第6期科学技術・イノベーション基本計画ではSociety 5.0を、一人ひとりが多様な幸せ(well-being)を実現できる社会として表現しています。
それではSociety 5.0で中心的な役割を担うものは何でしょうか?内閣府作成の資料によると、フィジカル空間からセンサーとIoTを通じてあらゆる情報を集積、AIがそのビックデータを解析し、高付加価値を現実空間にフィードバックがSociety 5.0の概要となります。人で例えると、センサーが口、ビッグデータが食料、IoTが神経ネットワーク、AIが頭脳、ロボットが筋肉に対応するような世の中です。その中でも重要な要素が食料に対応するビッグデータです。食料がなければ人も社会も機能することはできません。
そのデータを扱うデジタル人材育成の一環として文部科学省では「数理・データサイエンス・AI教育プログラム認定制度」を推進しており、経済産業省では「地域DX促進活動支援事業」に取り組んでいます。成蹊大学でもSociety 5.0において活躍できる人材を育成するため、2021年度に「データサイエンス副専攻」を開設しました。また本研究所でも集中講義や講演会を企画し、Society5.0が抱える課題の検討、データサイエンス教育の普及に力を入れてまいりました。また所内のDXの取り組みとしてキャンパスのデジタルツイン化を掲げ、メタバースの構築、AIチャットボットの実装などにも取り組んでまいりました。
Society 5.0の実現のためには課題は山積しています。少子高齢化、格差社会、環境保全、防災、インフラ整備、教育・子育て。これらの課題に取り組み解決するには2022年度JEITA技術戦略部会で提言されているように、「Connected Society(繋がる社会)」の具現化が初めの一歩となります。大学、企業、自治体、周辺住民の皆さんとの連携と共創が今後ますます重要となっていきます。またSociety5.0 研究所の所員は理工系の教員だけではなく、法律、経済、経営、文学を専門とする教員もおり、また本研究所に所属する客員フェローの先生方のバックグラウンドも多岐に渡ります。令和3年に改正された科学技術・イノベーション基本法においても、人文・社会科学と自然科学を含むあらゆる知の融合による「総合知」の重要性が謳われております。本研究所でも様々な専門知識と経験を活かし、社会が直面する諸課題を解決すべく研究と教育に尽力してまいります。今後も、異なる分野の知見と経験を活かしながら、教育・研究・社会実装を通じて、社会課題の解決に真摯に取り組んでまいります。皆様の変わらぬご支援とご指導を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。
略歴
成蹊大学理工学部理工学科教授/統計数理研究所客員教授
慶應義塾大学理工学部卒業
総合研究大学院大学複合科学研究科修了(博士 統計科学)
専門は生物統計、医療統計、機械学習、データサイエンス
日本統計学会、日本計量生物学会、応用統計学会に所属
日本計量生物学会誌編集委員、Japanese Journal of Statistics and Data Science, Associate Editor、応用統計学会理事などを歴任