観測所紹介
観測所の歩み


観測場所(気象観測露場)の移転マップ:
地理院地図(国土地理院)を加工して作成
A:旧露場 1926-1961
B:露場 1962-1985
C:現露場 1986-
現露場位置:東経139度34.3分 北緯35度43.0分(世界測地系)
-
- 1925
- 観測露場と百葉箱を設置、成蹊高校教諭・加藤藤吉氏が生徒とともに試験的な観測を開始
-
- 1926
- 加藤氏と生徒による正式な気象観測を開始、地上気象観測方法に準拠した毎日10:00の定時観測
-
- 1928
- 雲量と湿度の観測を開始
-
- 1929
- 気圧と通年結氷降霜の観測を開始
-
- 1931
- 日照時間の観測を開始

旧理化館南側にあった気象観測露場と百葉箱。右手後方に見えるのは成蹊大学本館。 -
- 1939
- 結氷厚さの測定を開始
-
- 1942
- 東京管区気象台甲種補助観測所(区内観測所)の「吉祥寺観測所」に指定
-
- 1953
- 9:00定時観測に変更
-
- 1959
- 成蹊気象観測所設置(当初は成蹊気象天文観測所)
-
- 1962
- 成蹊中学・高等学校の新校舎建築に伴い、露場を中学校前庭北側に移転
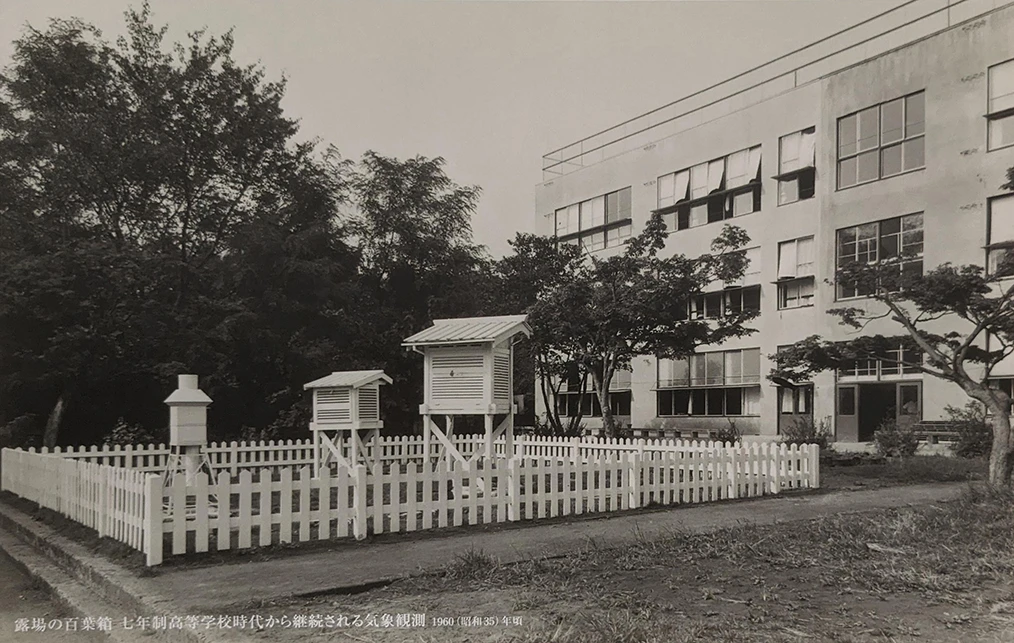
露場の百葉箱 七年制高等学校時代から継続される気象観測 -
- 1963
- 「東京タワー」、「富士山」の視程日数観測開始
-
- 1976
- 気象庁による区内観測所の委託業務終了
-
- 1986
- 露場を中学・高等学校特別棟南側に再移転(現在に至る)

南東側から見た露場と百葉箱 -
- 1992
- 降水pH測定開始
-
- 1994
- 自動気象観測装置(大田計器OTAC-2000)設置
-
- 2002
- 降水電気伝導度測定開始
-
- 2015
-
黒球温度計設置(暑さ指数)測定開始
自動気象観測装置集計器を更新(大田計器 WL-2250 AWS Data Logger)
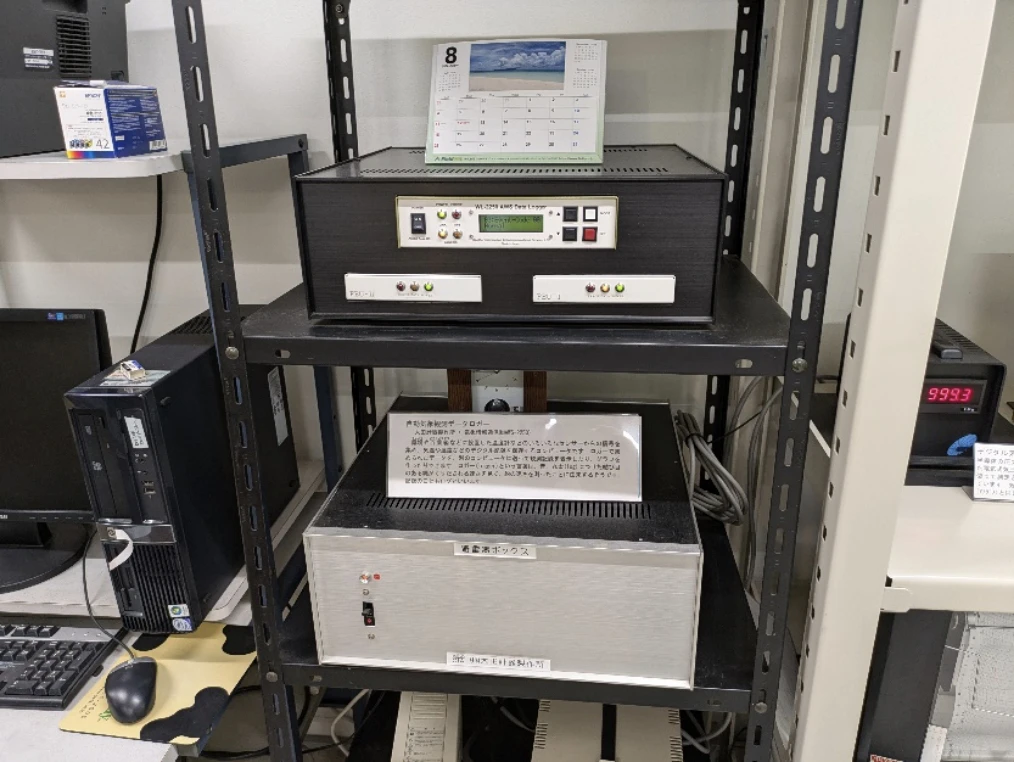
-
- 2023
- 三上岳彦所長、田中博春副所長 着任
