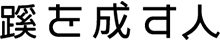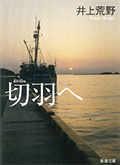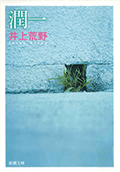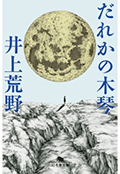小説家の道を歩まれたのは、やはりお父様の影響が強かった?
やはり環境は大きいでしょうね。江國香織さんもお父様が物書きで、彼女と話しても感じるんですけれど、そういう家に育つとプロの物書きになるってことをあまり特別なことに思わないんですよ。普通だと、物書きになるなんて大変だよとか言われそうですが、そういった圧力みたいなものがなかった。
父からは様々な本を薦められて、それも影響していると思います。高校生くらいになると、もう大人の本を持ってきて...。最初はトルーマン・カポーティの「夜の樹」という短編集。その中に「ミリアム」っていう短編があって、これだけでもいいから読んでみろと。老いや死に対する恐怖、諦念みたいなことがテーマで、16歳くらいの若さで読んでもピンとこないわけです。でも、父はものすごく面白いと言う。父は、本当に俺って小説が上手いよな、ドストエフスキーの次に俺が上手いかもな、っていうのが口癖で。そんな父が面白いって言うんだから、面白い小説はこういうものだって思うわけです。もう刷り込みですね(笑)。私にとってそれが最初の文学への認識だったので、今でも私の素地、根底となっています。

![SEIKEIJIN [成蹊人]](/gakuen/ss/web_mag/logo01.png)