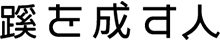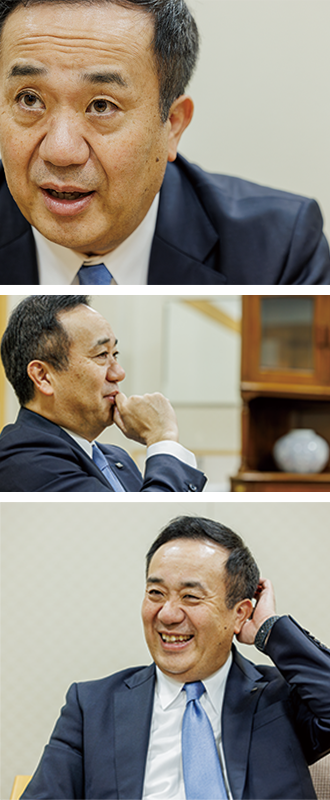(本取材は2025年2月に行われたものです)
成蹊は、ずっと付き合っていける仲間や友人に恵まれた場所
成蹊大学を受験したのは、兄の友人が成蹊に通っていて「少人数教育の学校だから学生同士の仲が良くて楽しいよ」と薦めてくれたからです。当時住んでいた横浜からは遠かったものの、受験で初めて訪れた吉祥寺の街の雰囲気がとても気に入りました。歴史を感じる校舎やケヤキ並木も印象的で「ここで学びたい」と心から感じたことを今でもよく覚えています。
入学後は小学生の頃に始めた剣道を続けるために、剣道部に入部。活動は土日も含めて週6日で、ほぼ休みはありません。掃除を終えて帰路につくのは夜9時を過ぎる日も多く、横浜から約2時間かけて通学していた私が帰宅すると、日付が変わっていることも。
そんな時に助けてくれたのが体育会の部活仲間たちです。なかでも同じ武道系の人たちとは仲が良かったですね。練習で遅くなった日は、空手部のほか、なぜか学内では武道系に分類されていた応援団の仲間の下宿先によく泊めてもらっていました(笑)。
文字通り剣道漬けの日々でしたが、田中英夫先生の英米法ゼミのことはよく覚えています。当時にしては珍しいディスカッション中心のゼミで、とにかく毎回議論を重ねます。私自身、意見をはっきり言うタイプだったので、このスタイルが肌に合っていたのでしょう。人と意見を戦わせることの面白さはここで学びました。
ゼミに限らず、多くの授業が少人数制だったのでクラスメイトとは仲が良かったですね。テスト前などには、まるで団体戦のように勉強でも助け合いました。20人ほどの大人数で伊豆や富士五湖へ旅行に行ったことも。部活の仲間やクラスメイトとは今でも交流が続いています。
「剣は人なり、心なり」
が私のなかには息づいている。

自分の強さも弱さも、謙虚に見つめることの大切さ
剣道部では主将を務め、3年次には団体戦で全日本大会に出場する機会を勝ち取りました。成蹊にはスポーツ推薦がないのですが、それでも優れた成績を残せたのは部員が一丸となって練習に励んだからこそです。とにかく誰一人欠けることなく全員で強くなることを目指していました。その背景にあったのは「打って反省、打たれて感謝」という剣道の考え方です。この言葉に示されているのは「常に謙虚であること。相手のことを敬うこと」の大切さ。剣道は、勝ってガッツポーズをしたら相手への礼節を欠く行為として判定が無効になる世界。学生時代の私はそこまで謙虚にはなれませんでしたが(笑)、自分さえ良ければいいのではないという考えは今も私の中にしっかりと息づいています。
剣道から学んだことは本当にたくさんあります。「剣は人なり、心なり」という言葉もそのひとつ。江戸時代の剣客、島田虎之助の格言です。この言葉をもって「剣道には、自分の強いところも弱いところも、すべて出る。だからこそ自分の強さを生かし、弱さも感じながら、修行に励まねばならない」と恩師に教えられました。この言葉を目にすると今でも、謙虚に自分を見つめることが大事だと姿勢を正されますし、同時に、自ら決断したときには躊躇せず、思いきって打ちに出ることの重要性も感じます。

![SEIKEIJIN [成蹊人]](/gakuen/ss/web_mag/logo01.png)