ある日の授業
文学部国際文化学科 演習Ⅱ(担当:川村陶子教授)が東京国立近代美術館でフィールドワークを行いました
お互いの国を「知る」ということ―文学部国際文化学科が卒業生ゲスト講義を開催!
文学部 墓田ゼミでゲストスピーカーに講演いただきました
文学部「文化人類学入門Ⅰ」で、アイヌ文化・アイヌ語を伝える活動を行う関根摩耶さんに講演いただきました
「国際文化英語演習<2>」の履修者有志がドイツ・ベルリン自由大学大学院の学生とオンラインで国際交流をしました
黒宮亜紀先生(メキシコ国立南部国境大学El Colegio de la Frontera Sur准教授)に、現地から「メキシコ南部の国境:国境の町と国境を越える人々」というタイトルで講演いただきました
成蹊大学「プロジェクト型授業」を実施している文学部国際文化学科の細谷広美教授の「国際文化基礎演習Ⅳ」(2年生対象)で、メキシコとオンラインでつなぎ(時差15時間)、黒宮亜紀先生(メキシコ国立南部国境大学El Colegio de la Frontera Sur准教授)に、現地から「メキシコ南部の国境:国境の町と国境を越える人々」というタイトルで講演いただきました。細谷教授の「プロジェクト型授業」では、人口の約2割が外国籍住民である群馬県邑楽郡大泉町観光協会の協力を得て、日本における移民政策と移民の方たちの現状を、移民政策の不在を含めて考察するとともにフィールドワークの基礎を学んでいます。
黒宮先生は、都市人類学及び移民研究を専門とされる気鋭の人類学者で、メキシコのイベロアメリカーナ大学で博士の学位を取得された後、現在チアパス州タパチュラ・キャンパスで、移民とトランスボーダープロセス研究グループに所属し調査研究されています。講演では、「移民」とはどのような存在か、国境の意味の多様性、グローバル化における一つの結節点として国境の町というサイトで起こっている現実についてお話しいただきました。メキシコというとトランプ政権時代に国境に壁を作る計画が進められたことが知られていますが、実際にはメキシコは「移民送出国」であるだけでなく、「移民受け入れ国」、「移民通過国」でもあります。歴史的にも多くの亡命者/移民/難民を受け入れてきています。
黒宮先生が研究されているタパチュラ市は、中米グアテマラとの国境に位置し、日常的に人々が仕事や買い物、教育のために正規・非正規ルートを問わず国境を往来し、あるいは国境をまたいで家族が交流するということがみられます。一方で、中南米からアメリカ合衆国への移住を目指す人々の通過点ともなってきました。しかし、2018年頃からハイチ出身者が急増するという現象が起こっています。ハイチでは地震によって多くの難民が生まれ、ワールドカップやオリンピック開催に伴う労働需要によってブラジルに渡った人々が、その後職を失い、アメリカ合衆国への移住を目指してタパチュラ市に集まっているのです。現在はハイチからの人々に加え、同様にアメリカ合衆国への移住を目指すアフリカ、アジア、中東出身者等、世界各地から様々な人々が集まり滞在しています。人口わずか36万人の街で、2022年度だけでも7万人以上の難民申請がなされており、このため、移民、難民を支援するIOM(国際移住機関)、UNCHR(国連難民高等弁務官事務所)、ユニセフをはじめとする国際機関や国内外のNGOなど、50以上の外部機関・組織が集まるという状況も生まれていることが伝えられました。
講演後は、実際にフィールドワークをおこなう際のアドバイスなど、学生たちの質問にも一つ一つ丁寧に答えていただきました。





文学部国際文化学科 有富純也教授のゼミで、奈良県に調査旅行へ行きました。
日本を中心に、東アジアの様々な文化や歴史について学ぶ有富ゼミでは、長期休暇を利用して、日本各地の史跡等の調査のためフィールドワークを兼ねた調査旅行を実施しています。新型コロナウイルス感染症が広まって以降、調査旅行を中止せざるを得ない状況でしたが、今年は感染対策をしっかりと行った上で、1泊2日で奈良県の文化財や史跡を巡りフィールドワークを実施しました。
1日目は東大寺や正倉院に赴きました。天平文化の華でもある東大寺法華堂の仏像を見学し、二月堂からは眼下に広がる大仏殿や奈良町の様子を確認できました。正倉院では、宮内庁正倉院事務所の佐々田悠先生にご案内いただき、正倉院宝物の歴史などを学びました。
2日目は奈良文化財研究所や興福寺の発掘現場にお邪魔しました。奈良文化財研究所では、発掘された木簡がどのように洗浄・保管・保存されるのか、肉眼では読めない木簡の文字をどのように読むのか、などについて山本祥隆先生にご教示いただきました。興福寺の発掘現場では、発掘とは何か、現在どのような発掘が行われているか、などを奈良文化財研究所の垣中健志先生にレクチャーしていただきました。
両日ともに暑かったものの晴天で、有意義な研修旅行になりました。参加者からは、「普通なら絶対に行けないところに行くことができたり、見られることができたり、とても楽しかったです。」という感想がありました。
学生たちは、日頃は教室で文献や資料を用いて史跡や文化財について調べていますが、現地で実物を見て調査することで理解度は格段に増したようです。
有富ゼミについての詳細はこちら



川村陶子教授の夏期集中ゼミで、国連開発計画(UNDP)勤務の卒業生がゲスト講義を行いました
文学部国際文化学科 川村陶子教授の学部3・4年合同夏期集中ゼミで、国連開発計画(UNDP)駐日代表事務所ユース担当コンサルタントの天野裕美さんがゲスト講義を行いました。
天野さんは川村ゼミの第1期生で、2003年に成蹊大学を卒業後、英国エセックス大学大学院で人権学の修士号を取得し、欧州・中東・アフリカ地域で国際協力の業務を歴任されています。その活躍の範囲は、JICA青年海外協力隊員(ヨルダン)、在カタール日本大使館専門調査員、UNDPスーダン事務所職員、UNHCRジュネーブ本部ユース・コンサルタントなど多岐にわたります。
プライベートでは学部留学時代の同窓生と国際結婚し、ビジネススクールローザンヌでMBAを取得しつつ長女を出産。現在は東京でご家族と暮らしながらUNDP駐日代表事務所で、UNDP・シティファウンデーション共催の若手社会起業家支援プログラム「Youth Co:Lab(ユース・コーラボ)」の運営を担当されています。
ゲスト講義では、勤務先であるUNDPの活動やYouth Co:Labプログラムの紹介に続き、天野さん自身のキャリア形成についてのお話がありました。学生時代から国際協力の仕事を志し、国際機関勤務を目標に学位取得やインターンシップ、フランス語やアラビア語の修得等を行ってきたこと、JICAの制度を利用して経験を積んだことなどを具体的に語っていただきました。国際協力の仕事にも緊急援助から青少年支援、バックオフィスまでさまざまな分野や職種があり、自分の関心と特性にあわせたキャリア形成が重要だというお話など、卒業や就職活動を控えた現役学生への貴重なアドバイスもいただきました。
後半はゼミの後輩とフリートークで交流。「ハードな国際業務に携わりながらワークライフバランスをどのように達成したのか」「外国でマイノリティとして暮らすことの苦労は」などさまざまな質問が出て、あっという間に時間が過ぎました。
4年生の参加者は講義の後でこんな感想を寄せています。「豊かな人生経験やキャリアを積まれた天野さんから、学生時代を振り返る形でお話があり、自分と重ね合わせることで非常に刺激的な時間となりました。何よりも天野さんの人柄から人を惹きつける魅力を感じ、これから社会に出る私たち学生にとって、大切なものを教えていただいたように思います。」
UNDP駐日代表事務所のウェブサイトはこちら
Youth Co:Lab Japanの紹介はこちら



アイヌ民族文化財団から講師を招き、特別授業が行われました
2022年7月4日(月)・6日(水)の2日間、細谷広美教授(文化人類学)のゼミで、アイヌ民族文化財団から関根摩耶さんを講師にお招きしお話を伺いました。細谷教授はアンデスの先住民文化に関する書籍を複数言語で数多く出版する他、「先住民族の権利に関する国連宣言」(2007年)の採択に関わったジュリアン・バージャーの書籍を翻訳出版しています。
関根さんは、アイヌ民族初の国会議員となった故萱野茂氏の故郷である北海道平取町二風谷(にぶたに)出身で、お祖母様が樹皮を用いた繊維を草木染し織るアイヌ伝統の衣服制作の第一人者でいらっしゃるなど「アイヌ」が当たり前に存在する環境で育ったそうです。高校生の頃からアイヌ語を広める活動を始め、慶応大学在学中には各種講演やラジオ番組、YouTube等を通じてアイヌ文化を発信。今年の3月に大学を卒業し、現在はフリーランスとしてこれまで以上に精力的にアイヌ文化を伝える活動をされています。
授業では、両日とも「トナカイ」「ラッコ」「コンブ」などの身近な単語がアイヌ語起源であることや、アイヌ伝統の工芸品や食べ物、関根さんの幼少時代のエピソードなどたくさんの写真とともにアイヌについての紹介がありました。
4日の3・4年生のゼミでは、ニュージーランドの先住民族マオリの人々が言語復興に用いた言語学習法「テ・アタアランギ」を通じて、アイヌ語を学ぶワークショップがおこなわれました。テ・アタアランギの時間が始まったらアイヌ語以外は一切使用せず、全てジェスチャーで教わります。学生たちは初めて聞く言葉に戸惑っていましたが、何度も反復練習することで自己紹介と買い物をする際の一連の会話を覚えました。楽しかったという感想とともに、「メモなどもせず、自分の中に言葉を取り入れて言葉にするため、非常に頭を使う方法で、だからこそ確実に身に付く」という感想が寄せられました。
6日の2年生の基礎演習では、体の部位を表す単語を、替え歌にあわせて体を動かし歌いながら教わりました。ゲーム感覚で楽しみながらアイヌ語に触れました。文字がない世界の人々の記憶力の強靭さ、「カムイ」を通じたアイヌの人々の世界観、人生観、アイヌは交易の民であったこと、狩猟、漁撈、採集などによって得られる豊かな食材をもとにした料理の話など、様々なことが伝えられました。
関根さんは、「私たちのことを「アイヌ」と括ることによって、もうそこから私たちは他の人たちとは異なる存在に区別されている気がする。みなさんの生まれた地域にもそれぞれの文化があり、そのルーツを持っている。アイヌが特別ではない。あなたも私も同じ。文化は異なっているからおもしろい。違いをどう生かすかが大切」というメッセージが伝えられ、同世代の関根さんの言葉だからこそ考えさせられることも多く、学生たちにとって大変貴重な時間になりました。
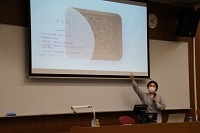


「国際文化英語演習<2>」の履修者有志がドイツ・ベルリン自由大学大学院の学生とオンラインで国際交流をしました
文学部川村陶子教授が担当する「国際文化英語演習<2>」(文学部国際文化学科2年次必修科目)の履修者有志とドイツ・ベルリン自由大学大学院のコネリア・ライヤー教授のゼミ生が5月にオンラインで国際交流を行いました。 2021年度・2022年度に続き3回目のコラボレーションとなります。 ライヤー教授は、ベルリン自由大学大学院東アジア研究プログラム(GEAS)副長・日本学部教授で、主な研究分野は、日本の地域や食、グローバリゼーション、科学技術です。コロナ禍で国際移動が妨げられていた2021年度、川村教授がライヤー教授と「オンラインで教育交流活動ができないだろうか」と話し合い、アイディアが生まれました。 ライヤー教授の大学院ゼミでは、日本の食文化を題材として「日本研究のメソッド(方法)」を修得しています。今回の交流は、ドイツの大学院生がZoomを使用して日本の学部生に日本語でインタビューをするというものです。ドイツ側は4名、日本側は6名が参加し、1対1ないし1対2のオンラインミーティングを行いました。 ドイツ側の大学院生は、本学の学生へメールでのアポイントメントやZoomのセッティングなどを行います。当日は、日常の食生活や海外における日本食などについてインタビューを実施。日本のポップカルチャーなど他の話題へ会話が発展することもあります。終了後は日独双方の学生代表がライヤー教授のゼミのブログに英語で報告記事を掲載します。 川村教授は、「ゼミのコラボレーションは毎回、日独双方の参加者に大変好評です。ドイツの学生には初対面の人と日本語でコミュニケーションし日本の若者の食生活を知る機会、日本の学生には日本語で気軽にできる国際交流体験となっています。 学生同士がメールでアポイントをとり、Zoomで面談するという方法もワクワク感につながっているようです。ライヤー教授とは今後も交流を続けていきたいですねと話しています。 今回参加したドイツ側大学院生の何人かは秋に来日予定だそうで、インタビュー相手とリアルでも会えるかも知れないと一同楽しみにしています。」と話していました。
国際文化学科2年 久保美月さんが書いた報告記事はこちら(外部リンク)
コネリア・ライヤー教授ゼミの大学院生が書いた報告記事はこちら(外部リンク)

細谷ゼミで映像作家の太田光海氏を招き、映像人類学について学びました
2021年10月28日(木)、文学部国際文化学科の細谷広美教授(専門:文化人類学)のゼミ「3年生対象演習Ⅱh」で、新進気鋭の映像作家の太田光海氏を招いて、映像人類学についてお話いただきました。神戸大学、パリ社会科学高等研究院大学で学んだ後、マンチェスター大学で学位を取得し5カ国語を操る太田氏。現在シアター・イメージフォーラムで公開中の作品『カナルタ 螺旋状の夢』は、国内外で数々の賞を受賞し、今後国内各地での上映が予定されています。
南米エクアドルのアマゾンに暮すシュアール族の家族とともに過ごし撮影した作品には、鮮烈な映像体験とともに、森の姿、人々と森との関係、アヤワスカを通じてのヴィジョン、地域をめぐる開発、薬草をめぐる新たな模索等、今を生きる先住民の重層的姿が映し出されています。
授業では、映像人類学の代表的な作品をご紹介いただきながら、今、映像人類学で何が目指されているかということについてもお話いただきました。ゼミ生以外にも映像人類学に興味がある学生が集まり、様々な質問が飛び交いました。



アイヌ民族文化財団から現役大学生の講師を招き、対面ゼミ・慶應大学との合同ゼミを開催
2021年6月16日(水)・17日(木)の2日間、細谷広美教授(文化人類学)のゼミで、アイヌ民族文化財団から関根摩耶さんを講師として派遣していただきお話を伺いました。細谷教授は先住民族の権利に関する国連宣言の採択に関わったジュリアン・バージャーの書籍を翻訳する他、アンデスの先住民文化に関する書籍を数多く出版してきています。
日本では2019年にアイヌ新法(アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律)が成立し、昨年(2020年)には北海道の白老町に国立アイヌ民族博物館(通称ウポポイ)が創設されました。また、マンガ・アニメ『ゴールデンカムイ』が話題となり、同作は大英博物館で開催されたマンガ展(2019年)で大きくとりあげられています。講師の関根さんは現在慶応大学の4年生で、アイヌ民族初の国会議員となった故萱野茂氏の故郷でもある北海道平取町二風谷(にぶたに)出身です。各種講演やラジオ番組、YouTube等を通じてアイヌ文化を発信してきていらっしゃいます。
16日は基礎演習(2年生)の対面ゼミ、17日はオンラインで関根さんが所属する慶応大学のゼミと本学3、4年生の合同ゼミを開催しました。お話は「シシャモ」「ラッコ」、ファッション雑誌「non-no」(「花」の意)などの身近な単語が実はアイヌ語起源であるということからはじまり、町の活動として子供の頃からニュージーランドの先住民族マオリの人々の地を訪れ交流してきていること。樹皮を用いた繊維を草木染し織る衣服制作の第一人者のお祖母様から様々なことを学んだこと。宗教、工芸品、食べ物、歌、楽器、踊り、アイヌ語のミニ講座など盛沢山でした。近年は10代、20代の若者たちがSNSを通じてアイヌ語で会話をしているそうです。「カムイ」の話から最後に「天から役目なしに降ろされたものは一つもない(kanto oro wa yaku sak no arankep shiep ka isam)」という世界観が伝えられました。
締めくくりとして関根さんから「私たちのことを「アイヌ」と括ることによって、もうそこから私たちは他の人たちとは異なる存在に区別されている気がする。結局それがアイヌだけでなく他の多様な文化や人を区別、排除することにつながると思う」「いろいろな価値観、いろいろな人を受け入れるのが当たり前になるような社会になれば素敵なのではないかと考え、そのきっかけにアイヌが成り得るのではないかと思いながら発信を続けている」いうメッセージが伝えられ、同世代が多様な経験をしていることを知るダイバーシティの観点からも貴重な時間となりました。


