経済学部内藤朋枝
子どもを持つ女性のワーク・ライフ・バランスに関する研究
共働きが当たり前の時代に
主人公が帰宅すると、母親はいつも家にいて、食卓には手作りの料理が並び、「ご飯よ」と声がする。小説や漫画などで、そんな場面を目にすることがよくあると思います。ところが、こうした家庭の様子は、随分と前に当たり前ではなくなっています。1990年ごろから両親とも収入を得るために働く「共働き世帯」の方が多くなりました。現在では共働きがむしろ一般的です。それでも、社会のイメージや制度が過去のまま、という部分も多く、現実とのギャップが女性たちにとって負担になっていることが少なくありません。
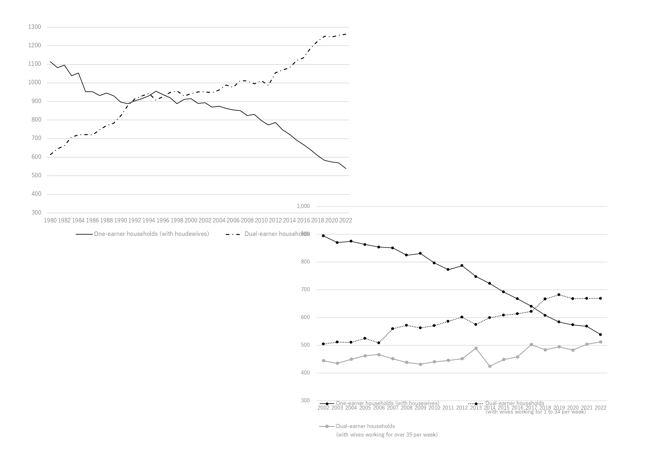
図1:1990年代から共働きが多い
変わらない雇用慣行と女性の時間の使い方
子育てしながら働く女性が多くなりましたが、職場の環境はなかなか変わりません。例えば、長時間労働や会社の都合に合わせた異動などはよくあり、子育てとの両立はとても大変です。1日は24時間しかありませんので、その中で仕事や家事、育児、普段の生活時間をやりくりする必要があります。子どもが小さいうちは病気などで手がかかることも多く、やりくりは簡単ではありません。家族以外のサポートを得にくい家庭では、女性がひとりで多くの役割を背負い込むこともあります。こうした状況について、社会調査で得られた量的データを使い、計量経済学の手法を用いて、女性たちの生活が少しでも楽になるヒントを見つけようとしています。

図2:仕事が終わればスーパーに直行
支援の広がりと新しい課題
最近では、企業や行政がさまざまな取り組みを進めています。男性の育児休業やリモートワークの導入なども一例です。このような制度が女性のワーク・ライフ・バランスにどんな影響を与えるのか、研究を通じて明らかにしようとしています。また、子どもが成長すると生活も変化します。現在は小さな子ども向けの支援が多いですが、小学校に入学してからの子育てや、子どもの性別・親の性別の組み合わせによる違いなど、より細やかな視点での検討も必要です。例えば、学童保育の利用状況や放課後の過ごし方、宿題の見守りなど、親の関与が求められる場面は意外と多くあります。こうした実態に即した支援策の提案や、誰もが働きやすく暮らしやすい社会づくりに貢献できるように研究を進めたいと思っています。
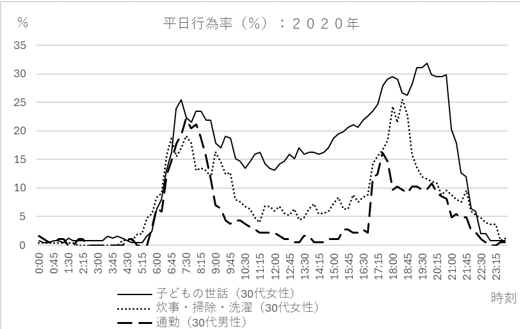
図3: 家事・育児は集中しがち(内藤2024)
Profile
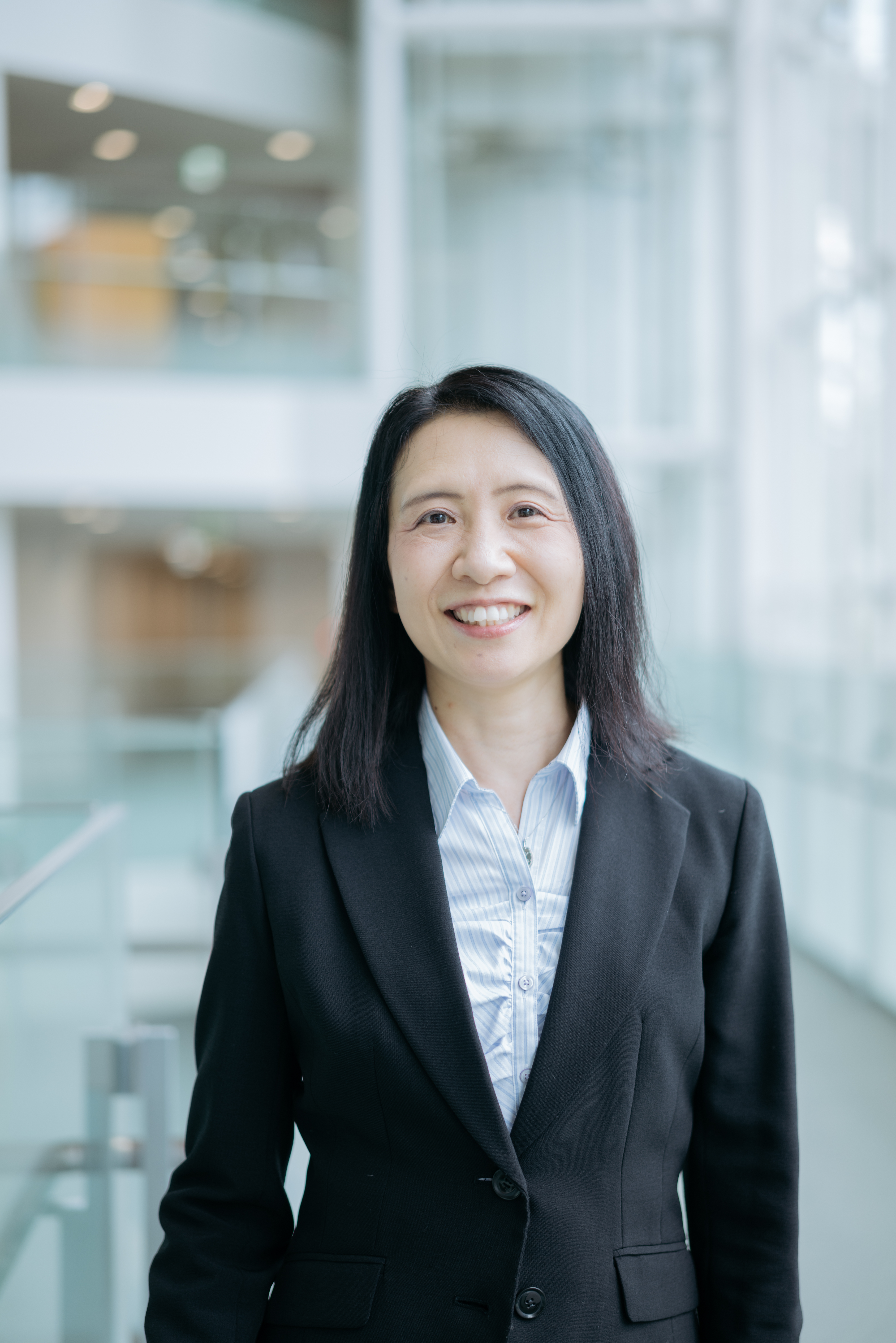
経済学部
内藤朋枝
- 専門分野 労働経済学、社会保障論
- 担当授業 社会保障論A・B、医療経済学、行動経済学、上級ゼミナールⅠ・Ⅱなど
- 研究に関連するコンテンツ
- ・リサーチマップ


