経営学部福澤光啓
すぐれた価値を創りだす組織の能力の探求
ものづくりは笑顔づくり
私たちは、新しい製品やサービスを利用して、より便利で豊かに生活しています。これらは人々のたゆまぬ創意・くふうによって実現されたもの、すなわちイノベーションの成果です。この新たな価値(顧客や社会が抱えている問題や課題を解決するもの)を創りだす活動を効率的に遂行することが、企業および経済・社会の成長の原動力となります。社会や顧客、作り手(企業)、一緒に働くなかまたちの「すべてがうれしい状況をつくりだす」という、難しいけれども絶大なインパクトを社会・経済にもたらすことが、優れたイノベーションのマネジメントのあり方であると私は考えています。このイノベーション活動を成功裏に導くための企業の戦略と組織運営のあり方の両方について実証的な研究をしています。特に注目しているのは、製品の開発や生産などに代表される「ものづくり」活動であり、それを担う製造企業です。
よい価値の流れを実現する組織の特徴
「A社が高い世界市場シェアを獲得できているのは、優れた生産現場の能力にもとづく高品質かつリーズナブルな製品を短納期で提供しているからである」、「△△市場における競合企業と我が社の製品開発能力を比べると□□くらいの違いがありそうだ」などと研究者や実務家が言う際の「能力」とは一体何か?それをどのように把握・測定できるのだろうか?このような疑問について経営学では「組織能力(Organizational capability)」という概念を用いて研究が進んできました。特に、高い成果を発揮する生産システムの特徴については、自動車産業をはじめとする国際比較調査により、日本の自動車企業のものづくり方式が欧米企業と比較して高い成果をあげていることが明らかになり、その特性がリーン生産方式(Lean Production System)と呼ばれ世界的に普及しました。私は、生産活動をはじめとして開発や調達、販売といった一連のものづくり活動に関わる「ものと情報のよい流れ(価値のよい流れ)」を実現する組織能力と経営実践の研究を行っています。
厳しい環境変化のもとで進化を続ける企業の経営のありかた
ものづくり企業をとりまく環境は厳しさを増しており、生き残り・成長を続けることがますます困難になっています。近年では、国際貿易摩擦や為替変動、自然災害、パンデミック、新興国企業との熾烈な競争、サプライチェーンの分断・混乱、製品の急速な複雑化・デジタル化の進展などが挙げられます。あわせて、グローバルに広がる様々な活動を見渡して、ものと情報の流れを可視化し、どこでどのような問題が起きているのかを迅速に発見し、その解決を図ることがますます難しくなっています。このような厳しい経営環境を生き抜き成長を続けるためには、卓越した戦略構想とものづくり活動の両者が不可欠です。そのための企業の本社・事業部の役割としては、各拠点・現場の能力を的確に把握しそれを活用・成長させられるような戦略構築・資源配分を行うことが重要です。一方、ものづくり現場の役割としては、弛まぬ能力構築を行い魅力的な製品の開発から販売に至るまでの一連の活動を有効かつ効率的に行うことが重要です。さまざまな環境変化に直面しても高い成果を発揮し成長を続けられる企業や現場の特徴を解明することが、ますます重要になっています。このような課題の大きさに比して、私は微力ではありますが、少しでも実践に役立つ知見を得るべく研究を進めています。
Profile
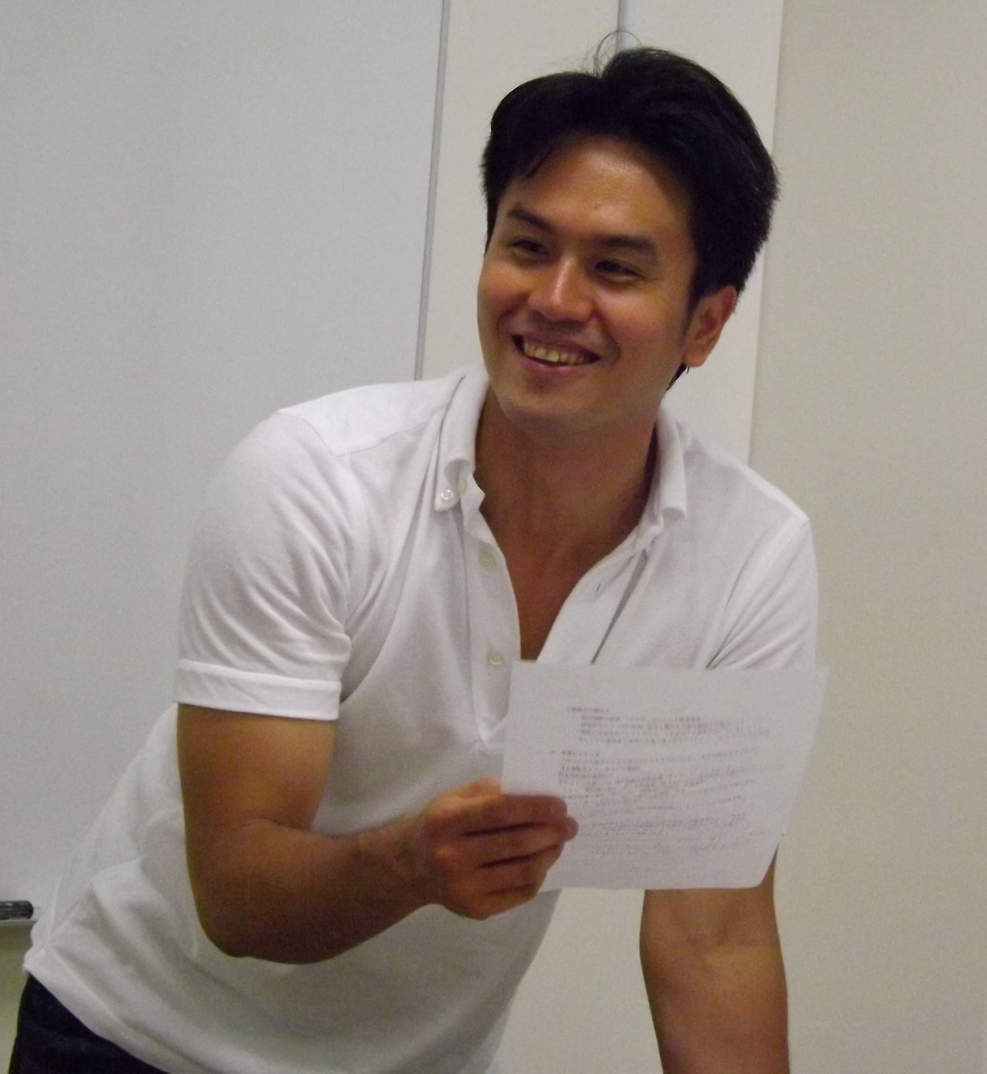
経営学部
福澤光啓
- 専門分野 経営戦略論、技術経営管理論
- 担当授業 経営戦略、イノベーションと製品開発、生産管理など
- 研究に関連するコンテンツ
- ・リサーチマップ


